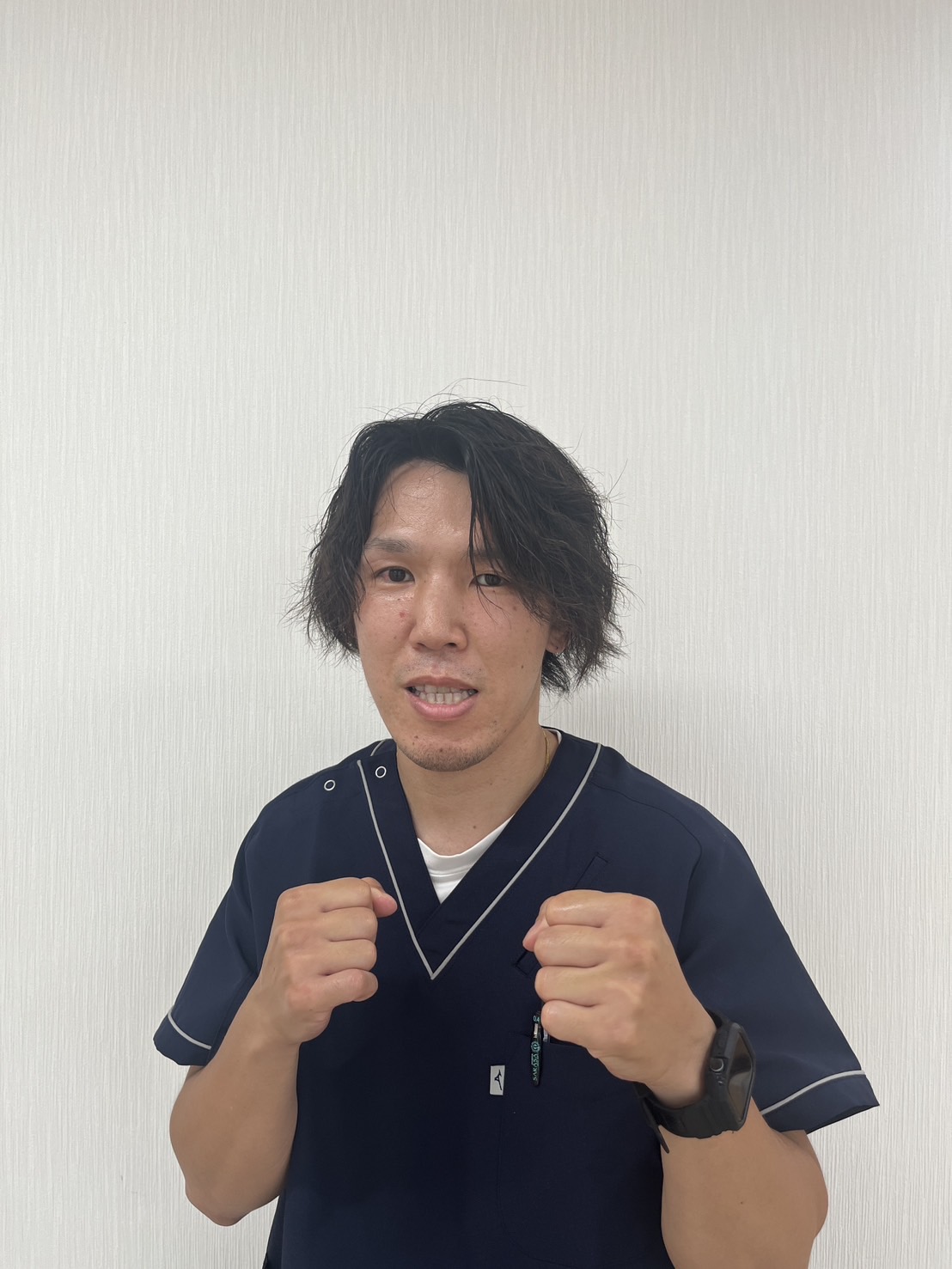ARTICLE
記事
- MEMBER
「頼られる存在」になるまで——自然体で導くエリアマネジメント
2025.06.23 Mon

無理せず、でも真剣に。
サニタには、あなたらしいリーダー像が描ける場所がある
「ガツガツ前に出るタイプじゃない」「人を引っ張るのは向いてないかも」
——そんなふうに思っている方にも、サニタはチャンスをくれる会社です。
頼られるリーダーの条件は、自然体で人と向き合い、チームの成長を支え続けること。
八重樫先生のようなエリアマネージャーの存在が、それを証明してくれています。